七五三は、子どもの成長を祝い、これまで支えてくれた方々に感謝を伝える大切な節目の行事です。
お祝いをいただいたときに欠かせないのが「お礼のメッセージ」。
しかし、いざ書こうとすると「どんな言葉でまとめればいいのだろう」「祖父母や職場の方にはどう送るのが正しいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、七五三のお礼メッセージの基本マナーから、祖父母・親戚・友人・職場など相手別にそのまま使える例文を豊富に紹介します。
短文で気軽に送れる一言メッセージから、手紙形式のフルバージョンまで幅広く揃えているので、状況に応じて選ぶことが可能です。
この記事を読めば、誰にでも安心して送れるお礼文が完成します。
七五三を迎えた喜びを、感謝の言葉とともに丁寧に伝えてみましょう。
七五三のお礼メッセージが大切な理由
ここでは、なぜ七五三のお礼メッセージが欠かせないのかを解説します。
ただ「ありがとう」と言うだけでなく、丁寧に言葉にして伝えることで相手の心に残ります。
また、お子さまの成長を一緒に喜んでもらえるきっかけにもなるため、七五三では特に重要です。
なぜお礼を伝える必要があるのか
七五三は子どもの成長を祝う日本の伝統行事です。
その際にいただくお祝いは、相手が時間や気持ちを込めて準備してくれた大切なもの。
感謝の気持ちは、言葉にしてはじめて相手にしっかり届きます。
たとえ短いメッセージでも、一言添えることで「大切に思っています」というサインになります。
| お礼を伝える意味 | 得られる印象 |
|---|---|
| 感謝を形にできる | 礼儀正しい人だと感じてもらえる |
| 子どもの成長を共有できる | 相手も一緒に喜べる |
| 人間関係を温める | 今後の付き合いがスムーズになる |
感謝の言葉が関係を深める効果
お礼の言葉は、単なる形式的なものではありません。
「〇〇も元気に成長しています」と近況を添えるだけで、温かいやり取りになります。
さらに「また会えるのを楽しみにしています」と結ぶと、自然に次の交流にもつながります。
何より大事なのは、かしこまるよりも素直に伝えることです。
そのひとことが、これから先の関係をより良いものにしていくきっかけになります。
七五三のお礼メッセージの基本マナー
ここでは、七五三のお礼メッセージを書くときに気をつけたい基本的なマナーを紹介します。
かしこまりすぎる必要はありませんが、ちょっとした工夫で相手にぐっと伝わりやすくなります。
ポイントは「感謝」「子どもの様子」「相手への気遣い」の3つです。
感謝を率直に伝える
まず最初に伝えたいのは、いただいた気持ちに対する感謝です。
「この度は七五三に際し、お祝いをいただきありがとうございます」と、シンプルに表現しましょう。
形式よりも「ありがとう」という素直な一言が、相手にとって一番心に残ります。
| 良い例 | 避けたい例 |
|---|---|
| 「この度はお祝いをいただき、心より感謝申し上げます。」 | 「お祝いありがとうございました。」(あまりに簡潔すぎる) |
子どもの成長や様子を添える
七五三は子どもが主役の行事です。
そのため「元気に成長しています」「神社で緊張しながらも笑顔で参拝しました」など、様子をひと言添えると温かみが出ます。
具体的なエピソードは、相手がほほえましく感じられるポイントになります。
| 表現の工夫 | 相手に伝わる印象 |
|---|---|
| 「着物をとても喜んで着ていました」 | 子どもの成長が目に浮かぶ |
| 「少し照れながらも元気に参拝しました」 | その場の雰囲気が伝わる |
相手への気遣いを忘れない
お祝いをくださった方が、遠方から来てくれたのか、わざわざ時間を割いてくれたのか。
その「行動」にも触れることで、より丁寧な印象を与えられます。
最後に「今後ともよろしくお願いいたします」と結ぶと、文全体がきれいにまとまります。
お礼の言葉は、感謝+子どもの様子+相手への配慮の3点セットが鉄則です。
| 文の構成 | 例 |
|---|---|
| ①感謝 | 「この度は心温まるお祝いをありがとうございました。」 |
| ②子どもの様子 | 「当日は元気いっぱいで、笑顔で参拝できました。」 |
| ③相手への気遣い | 「遠方よりお越しいただき、誠にありがとうございました。」 |
七五三のお礼メッセージの例文集【短文・一言編】
ここでは、すぐに使える短文の例文を紹介します。
メールやLINEでの送信、またはちょっとしたカードに書き添えるのにぴったりです。
短くても心が伝わる言葉を意識するのがポイントです。
祖父母に送る一言例文
「七五三のお祝いをありがとうございました。〇〇も元気に成長しています。」
「当日は着物を嬉しそうに着ていました。写真を同封しますので、ぜひご覧ください。」
祖父母には子どもの姿が伝わる言葉を添えるのがおすすめです。
| 送る相手 | 一言例文 |
|---|---|
| 祖父母 | 「〇〇が立派に参拝する姿を見守っていただきありがとうございました。」 |
| 祖父母 | 「お祝いのおかげで記念の日がより特別なものになりました。」 |
親戚に送る一言例文
「七五三のお祝いをいただき、ありがとうございました。」
「〇〇も喜んでおり、家族で楽しい時間を過ごすことができました。」
堅すぎず、感謝と近況をシンプルにまとめるのがコツです。
友人に送る一言例文
「七五三のお祝いありがとう!〇〇は着物姿を楽しんでいました。」
「成長を一緒に喜んでくれて、とても嬉しいです。また会いましょう。」
友人向けはカジュアルな言葉で気持ちを伝えると自然です。
職場関係に送る一言例文
「この度は七五三のお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」
「〇〇も元気に成長しており、無事に七五三を迎えることができました。」
目上の方には、礼儀を大切にしながらシンプルで丁寧な表現が好印象です。
| 送る相手 | 一言例文 |
|---|---|
| 職場関係 | 「平素よりお世話になり、この度も温かいお祝いをいただき感謝申し上げます。」 |
| 職場関係 | 「今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」 |
七五三のお礼メッセージの例文集【フルバージョン編】
ここでは、手紙やはがきにそのまま使える「フルバージョンの例文」を紹介します。
冒頭の季節の挨拶から、結びの言葉まで整った形にすることで、丁寧で心のこもった印象を与えられます。
フォーマルな相手や、特に感謝を伝えたい方におすすめです。
祖父母に送る手紙のフル例文
拝啓 朝夕の風がひんやりと感じられる季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
この度は〇〇の七五三に際し、温かなお祝いをいただき誠にありがとうございました。
当日は少し緊張していたものの、無事に神社で参拝を済ませることができました。
華やかな着物姿に、〇〇自身もとても嬉しそうで、家族にとって忘れられない一日となりました。
おじいちゃんやおばあちゃんに見守っていただけることが、私たち家族にとって大きな支えです。
これからも〇〇の成長をあたたかく見守っていただければ幸いです。
季節の変わり目ですので、どうぞお体を大切になさってください。
敬具
親戚に送る手紙のフル例文
拝啓 木々の葉が色づき、秋の深まりを感じる頃となりました。
皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。
この度は〇〇の七五三に際し、心温まるお祝いをいただき誠にありがとうございました。
おかげさまで無事にお宮参りを済ませることができ、家族一同喜びもひとしおでございます。
〇〇も成長した姿をお見せできたことを嬉しく思っております。
また皆様にお目にかかれる日を心待ちにしております。
どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
敬具
友人に送るメッセージのフル例文
〇〇へ
七五三のお祝い、本当にありがとう。
〇〇も着物を着るのをとても楽しみにしていて、当日は笑顔いっぱいで参拝できました。
子どもの成長を一緒に喜んでくれる友人がいることを、とてもありがたく感じています。
また遊びに来てくれるのを楽しみにしています。
これからもどうぞよろしくね。
職場関係に送るお礼状のフル例文
拝啓 秋冷の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度は〇〇の七五三に際し、過分なお祝いを賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで無事にお参りを済ませ、子どもも元気に成長しております。
日頃よりご指導いただいているうえ、このようにお気遣いいただき、深く感謝申し上げます。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
敬具
| 送る相手 | フルバージョンの文例の特徴 |
|---|---|
| 祖父母 | 子どもの具体的な様子を添えて、家族の温かさを伝える |
| 親戚 | 季節の挨拶と今後の交流への期待を込める |
| 友人 | カジュアルで親しみやすい言葉を中心にする |
| 職場関係 | 格式を大切にした丁寧な表現を心がける |
送る手段とタイミングの工夫
ここでは、お礼メッセージを「どの方法で」「いつ送るのか」という実務的なポイントをまとめます。
相手によって適した手段が変わるため、状況に応じて柔軟に選びましょう。
送るタイミングは七五三から1〜2週間以内が理想です。
手紙・はがきで送る場合
目上の方や年配の方には、手紙やはがきが最も丁寧な手段です。
直筆で書くことで、より誠意が伝わります。
はがきに写真を添えると、成長を共有できて喜ばれるケースが多いです。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 丁寧で誠実な印象を与えられる | 発送に時間がかかるため、遅れないようにする |
| 写真を同封できる | 形式ばかりに偏らず、温かさを忘れないこと |
メールやLINEで送る場合
友人や同年代の親戚には、気軽なツールで問題ありません。
短い文でも気持ちは伝わりますが、写真を添付するとより喜ばれます。
カジュアルすぎる表現は避け、最低限の礼儀を意識しましょう。
贈り物だけ受け取った場合
遠方の方など、直接会えない方から贈り物をいただいた場合は、まず到着の時点で受け取りのお礼を伝えましょう。
その後、写真や近況を添えたお礼メッセージを改めて送ると丁寧です。
「受け取りました」という安心感+「成長の報告」で、二段構えの気遣いになります。
| 状況 | おすすめの対応 |
|---|---|
| 直接会って渡された | その場で感謝+改めてメッセージを送る |
| 郵送で受け取った | すぐに「届きました」と連絡し、後日お礼状を送る |
七五三のお礼メッセージの現代的な傾向
近年は、七五三のお礼メッセージも多様なスタイルが増えています。
従来の手紙やはがきに加え、メール・LINE・SNSなどデジタルでのやり取りも一般的になっています。
相手との関係性や世代に合わせて使い分けるのが現代的なマナーです。
SNSやデジタルでの伝え方
InstagramやFacebookなど、SNSを活用する方も増えています。
ただし、公開範囲を配慮し、相手が不快に思わない形での投稿を心がけましょう。
一方でLINEやメールは「個別に伝える」方法なので、より気持ちがダイレクトに届きます。
SNSは「共有」、LINEやメールは「個別の感謝」と整理すると分かりやすいです。
| 手段 | 特徴 | 適した相手 |
|---|---|---|
| SNS投稿 | 写真や感謝を広く伝えられる | 親しい友人、フォロワー全体 |
| LINE・メール | 気軽に個別の感謝を送れる | 友人、親戚 |
| 手紙・はがき | 丁寧で正式な印象を与えられる | 祖父母、職場関係、目上の方 |
写真やデータを添えるときの注意点
スマホで撮影した記念写真を添えて送るのは、とても喜ばれる工夫です。
ただし、すべての相手が写真を求めているわけではありません。
祖父母にはフォトカードや現像写真が喜ばれ、友人や同世代にはデータ送付が便利です。
送り方も「相手にとって負担がない方法」を選ぶのが大切です。
| 相手 | おすすめの送り方 |
|---|---|
| 祖父母 | 現像写真やフォトカードを郵送 |
| 親戚 | 写真入りのはがきやメール添付 |
| 友人 | LINEアルバムや写真データの送信 |
まとめ
七五三のお礼メッセージは、いただいたお祝いに対して感謝を伝えるだけでなく、子どもの成長を共有できる大切な機会です。
基本は「感謝」「子どもの近況」「相手への配慮」の3つを押さえること。
そのうえで、相手との関係性に応じて、手紙・はがき・メール・LINEなど最適な手段を選びましょう。
短文でも心が伝わりますが、丁寧に整えたフルバージョンの手紙はより一層喜ばれます。
また、現代では写真やデジタルツールを添える方法も一般的になっています。
大切なのは形式にとらわれることではなく、素直に「ありがとう」を伝えることです。
この記事の例文を参考に、相手に合わせた温かいメッセージを届けてみてください。
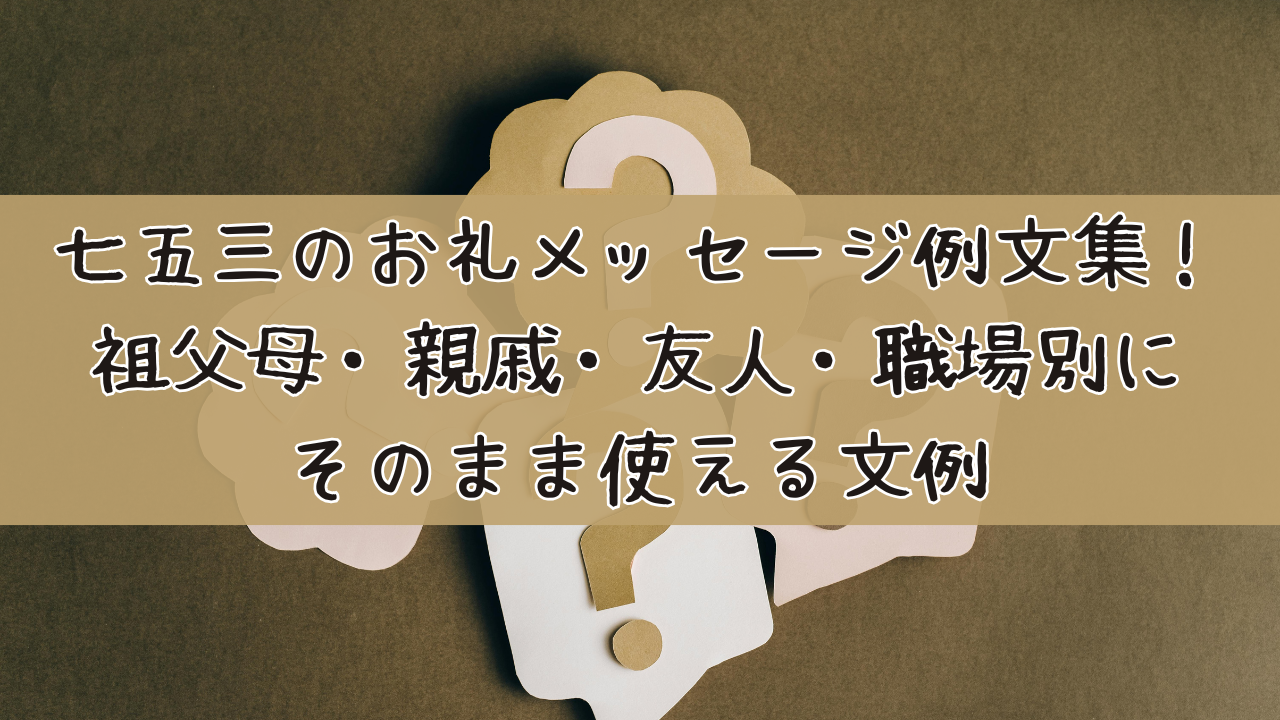
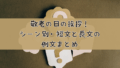
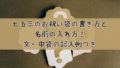
コメント