七五三を迎えるにあたり、気になるのが「初穂料(はつほりょう)」の準備です。
初穂料とは、神社でのご祈祷を受ける際に感謝の気持ちを込めて納めるお金のこと。
ただし、金額の相場やのし袋の選び方、表書きや中袋の書き方など、細かなマナーに迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、七五三の初穂料について金額の目安・のし袋と中袋の正しい記入例・実際に使える挨拶文まで、わかりやすく整理しました。
兄弟姉妹の場合の連名の書き方や、お寺で祈祷を受ける際の表書きの違いも例文付きで紹介しています。
この記事を読めば、初穂料の準備から渡し方まで安心して対応できるので、七五三のお参りを心から落ち着いて迎えられるでしょう。
七五三の初穂料とは?意味と基本マナー
七五三の「初穂料(はつほりょう)」とは、神社でご祈祷を受けるときに納める謝礼のお金のことです。
もともとは、その年に初めて収穫された稲や農作物を神様にお供えする習慣から生まれました。
現在では、お金をお供えとして包む形に変わり、七五三の参拝でも大切な準備のひとつになっています。
初穂料の由来と神社での位置づけ
「初穂」とは、その年に初めて収穫された稲や果物のことを指します。
昔は農作物そのものを神様に捧げていましたが、次第にお金を代わりに納める習慣が広がりました。
そのため「初穂料」という言葉には、神様への感謝の気持ちを形にしてお渡しするという意味が込められています。
お寺での呼び方との違い(御布施・祈祷料)
神社では「初穂料」と書くのが一般的ですが、お寺では御布施や祈祷料と表現されることが多いです。
どちらも「祈祷をしていただいたことへの感謝」を示すものなので、大きな意味合いは同じと考えて大丈夫です。
参拝先が神社かお寺かによって表書きの言葉を選び分けるのがマナーです。
| 参拝先 | 表書きに使う言葉 |
|---|---|
| 神社 | 初穂料・御初穂料・玉串料 |
| お寺 | 御布施・祈祷料 |
このように、初穂料はただのお金ではなく、感謝を表す心のこもったお供えだと意識すると、より丁寧な準備ができます。
七五三の初穂料の相場はいくら?
初穂料には明確な全国共通ルールはありませんが、多くの神社やお寺ではおおよその金額が決まっています。
ここでは、一人あたりの目安金額や兄弟姉妹で参拝する場合の注意点を整理します。
事前に参拝先に確認すると、より安心して準備できます。
一人あたりの目安金額
七五三の初穂料は一人あたり5,000円〜10,000円が一般的です。
神社によっては「初穂料は〇〇円」と指定されていることもあります。
迷ったときは公式サイトや電話で確認するのが一番確実です。
兄弟姉妹で参拝する場合の注意点
兄弟姉妹で同時にご祈祷を受ける場合は人数分の初穂料を用意するのが基本です。
例えば、二人の場合は10,000円〜20,000円を包みます。
一つののし袋にまとめても良いですし、分けても問題ありません。
地域や神社による違い
地域の慣習や神社の方針によって、相場が少し異なることもあります。
都市部の有名な神社では金額が高めに設定されていることもあり、地方の小規模な神社では5,000円程度が目安になることもあります。
大切なのは「決められた金額を気持ちよく納める」という姿勢です。
| 人数 | 目安金額 |
|---|---|
| 子ども1人 | 5,000円〜10,000円 |
| 子ども2人 | 10,000円〜20,000円 |
| 子ども3人 | 15,000円〜30,000円 |
金額はあくまで目安なので、「参拝先の決まりを優先する」ことを忘れないようにしましょう。
初穂料を包むのし袋の選び方
初穂料を包むときには、どんなのし袋を使うかが大切です。
のし袋は、色や水引の種類によって意味が変わるため、七五三にふさわしいものを選びましょう。
ここでは、水引の種類と市販のご祝儀袋を選ぶときのポイントを整理します。
水引の種類と意味(蝶結びと結び切りの違い)
七五三のような「何度でも繰り返したいお祝い事」には赤白の蝶結びを選びます。
蝶結びはほどいてまた結び直せることから、「繰り返して良い出来事」を表します。
逆に、結婚祝いなど「一度きりであってほしいこと」には結び切りを使うので、七五三では避けましょう。
市販のご祝儀袋を選ぶときのポイント
のし袋は白無地のものが基本ですが、文房具店やスーパーで売られている七五三用のご祝儀袋を選んでも問題ありません。
最近は「初穂料」と印刷されたシンプルなデザインのものも増えています。
ただし、キャラクター付きなどカジュアルすぎるデザインは避けたほうが無難です。
| 種類 | 七五三での適否 | ポイント |
|---|---|---|
| 赤白蝶結び | ◎ 適している | 七五三など繰り返したい祝い事に使う |
| 赤白結び切り | × 不適 | 結婚祝い向け、七五三では使わない |
| 印刷タイプののし袋 | ◎ 適している | 手軽で準備しやすい |
まとめると、七五三には「赤白蝶結び」ののし袋を選ぶのが基本です。
迷ったときは「七五三用」と明記されたご祝儀袋を選べば安心できます。
初穂料の表書きの正しい書き方
のし袋の表面に書く「表書き」は、七五三の初穂料で最も大事な部分です。
神様やお寺に失礼がないよう、正しい言葉と書き方を知っておきましょう。
ここでは、「初穂料」と「御初穂料」の違いや、子どもの名前の記載方法、そして実際に使える例文を紹介します。
「初穂料」と「御初穂料」の使い分け
基本的には「初穂料」と書けば問題ありません。
より丁寧に表現したい場合は「御初穂料」を使います。
どちらも正しいので、迷ったときは「初穂料」でシンプルにまとめると安心です。
子どもの名前の書き方(フルネーム・連名のルール)
水引の下にはご祈祷を受ける子どものフルネームを書きます。
親の名前ではなく、必ず子どもの名前を書くのが七五三のルールです。
兄弟姉妹の場合は、上から順に年齢の高い順に書くのが一般的です。
筆ペン・毛筆を使うときの注意点
表書きは毛筆または筆ペンで書くのが正式です。
ボールペンや万年筆は避け、どうしても用意できないときは黒のサインペンを使いましょう。
色は黒が基本で、薄墨や青いインクは使わないようにします。
実際の表書き例文
以下に、そのまま使える表書きの例文を紹介します。
| ケース | 表書き(上段) | 名前(下段) |
|---|---|---|
| 子ども1人の場合 | 初穂料 | 山田 太郎 |
| 兄弟姉妹2人の場合 | 御初穂料 | 山田 花子 山田 次郎 |
| お寺で祈祷を受ける場合 | 御布施 | 佐藤 美咲 |
フルバージョンの書き方例をまとめると、以下のようになります。
【フル例文1:神社・子ども1人】
上段:初穂料
下段:鈴木 太一
【フル例文2:神社・兄弟2人】
上段:御初穂料
下段:佐藤 花子 佐藤 翔
【フル例文3:お寺で祈祷】
上段:祈祷料
下段:高橋 陽菜
このように上に用途、下に子どもの名前という書き方を守れば安心です。
中袋の書き方と金額の記入ルール
のし袋の中に入れる「中袋」がある場合は、金額や住所をきちんと書きます。
細かいルールを知らないと迷いやすい部分ですが、例文を見ながら準備すれば安心です。
ここでは、漢数字の書き方、住所や名前の書き方、そして中袋がない場合の対応方法を紹介します。
漢数字・大字の使い方
金額は漢数字または大字(壱・弐・参など)で記入します。
これは、後から金額を書き換えられないようにするための工夫です。
例えば「一万円」は壱萬円と書きます。
住所と名前の書き方
裏面の左下に住所と名前を書きます。
縦書きが基本ですが、横書きしかできない中袋なら横書きでも大丈夫です。
大切なのは誰が納めたものかが分かるようにすることです。
中袋がない場合の対応方法
市販ののし袋の中には、中袋が付いていないものもあります。
その場合は、白い封筒の裏面左下に金額と住所を書きましょう。
どうしても封筒がないときは、のし袋に直接金額を書かなくても問題はありません。
実際の中袋の記入例
| ケース | 表面(中央) | 裏面(左下) |
|---|---|---|
| 一人分 | 金 壱萬円 | 東京都新宿区〇〇町1-2-3 山田 太郎 |
| 兄弟二人分 | 金 弐萬円 | 横浜市青葉区△△1-1-1 佐藤 花子 佐藤 翔 |
| 中袋なし | (記入なし) | 裏面に住所・名前・金額を記載 |
【フル例文:中袋の書き方】
表面中央:金 壱萬円
裏面左下:大阪市中央区□□2-3-4 田中 太一
このように表に金額、裏に住所と名前を書けば、どの神社やお寺でも安心して受け取ってもらえます。
初穂料のお金の準備と封入マナー
初穂料に使うお金は、普段のお支払いとは違い、丁寧に準備するのがマナーです。
ここでは、新札の準備方法やお札の入れ方、そして袱紗(ふくさ)での持参について紹介します。
ちょっとしたポイントを押さえるだけで、きちんと感謝の気持ちを伝えられます。
新札を準備する理由と入手方法
初穂料はできるだけ新札を使うのが望ましいです。
新札は「事前に用意しました」という気持ちの表れだからです。
銀行の窓口やATMの両替機で両替すれば簡単に入手できます。
どうしても新札がない場合は、折り目や汚れのないきれいなお札を選びましょう。
お札の入れ方の正しい向き
お札の向きにも決まりがあります。
一般的には人物の肖像が表を向き、かつ上側にくるように入れるのが基本です。
つまり、のし袋を開いたときに肖像画が正面を向いている状態です。
袱紗で包んで持参するのがベスト
のし袋はそのままバッグに入れず、袱紗で包んで持ち運ぶのが丁寧です。
袱紗は、ご祝儀やお祝いごとでお金を渡すときの正しい作法です。
色は紫や紺など落ち着いたものが無難で、男女問わず使えます。
実際の封入手順まとめ
具体的な流れを例文風にまとめると、次のようになります。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 銀行で新札を用意 | 前日までに準備しておく |
| ② | お札を正しい向きで中袋に入れる | 肖像が表・上にくるように |
| ③ | 中袋をのし袋に入れる | 表裏の向きをそろえる |
| ④ | のし袋を袱紗に包む | 紫や紺の袱紗がおすすめ |
【フル例文:封入マナーの流れ】
1. 銀行で新札を準備する。
2. 「壱萬円」と中袋に書き、肖像が上向きになるようにお札を入れる。
3. 中袋をのし袋に入れる。
4. のし袋を袱紗に包み、参拝当日に社務所へ持参する。
この流れを守れば誰から見ても丁寧で安心できる準備になります。
神社での初穂料の渡し方
初穂料は、ただ準備するだけでなく、神社での渡し方にもマナーがあります。
参拝当日に慌てないように、渡すタイミングや言葉遣いを事前にイメージしておきましょう。
ここでは、一般的な流れとそのまま使える挨拶例文を紹介します。
渡すタイミング(祈祷前と祈祷後)
多くの神社では祈祷の受付時に初穂料を納めます。
社務所で申込用紙を記入するときに一緒に渡す流れが一般的です。
一部の神社では祈祷後に渡す場合もあるので、案内に従えば問題ありません。
神職への伝え方・言葉遣いの例
渡すときの言葉は難しく考える必要はありません。
短く丁寧に伝えるのが基本です。
以下にそのまま使える例文を紹介します。
| 場面 | 例文 |
|---|---|
| 受付時に渡す | 「本日はよろしくお願いいたします。初穂料をお納めいたします。」 |
| 祈祷後に渡す | 「本日はありがとうございました。こちらをお納めください。」 |
| 不安なとき | 「初穂料はこちらでよろしいでしょうか。」 |
実際の渡し方の流れ
渡し方の流れをフル例文にまとめると次のようになります。
【フル例文】
1. 社務所の受付で「本日はよろしくお願いいたします」と声をかける。
2. 袱紗からのし袋を出し、相手に向けて差し出す。
3. 「初穂料をお納めいたします」と伝える。
4. 祈祷後は「ありがとうございました」と一言添える。
この流れを押さえておけば、どの神社でも落ち着いて丁寧に渡すことができるでしょう。
七五三の初穂料でよくある質問Q&A
初穂料は準備や書き方に細かいルールがあるため、迷う人が多いです。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
実際の声を想定した例文とあわせて確認しておきましょう。
Q1:金額がわからないときはどうすればいい?
A:迷ったときは参拝先の神社やお寺に確認するのが一番です。
電話で「七五三のお参りを予定していますが、初穂料はいくらでしょうか」と聞けば丁寧に教えてくれます。
金額を聞くことは失礼ではないので安心してください。
Q2:兄弟の名前を別々に書く必要がある?
A:兄弟姉妹で一緒に祈祷を受ける場合は、同じのし袋に連名で書いて構いません。
書き方の例文は以下の通りです。
| ケース | 表書き(上段) | 名前(下段) |
|---|---|---|
| 兄弟2人 | 御初穂料 | 佐藤 花子 佐藤 翔 |
| 兄弟3人 | 初穂料 | 山田 太郎 山田 花子 山田 次郎 |
年齢の高い子どもの名前を上に書くと、より丁寧な印象になります。
Q3:初穂料を現金で直接渡してもいい?
A:のし袋に入れずに渡すのは避けましょう。
財布から直接出すのはマナー違反とされるためです。
必ずのし袋に包み、袱紗に入れて持参してください。
Q4:筆ペンがなくても大丈夫?
A:できれば筆ペンが望ましいですが、なければ黒のサインペンでも問題ありません。
ただし、ボールペンや青インクは避けましょう。
Q5:初穂料の金額を多めに包んでも失礼ではない?
A:多めに納めること自体は問題ありません。
ただし、相場より極端に高額にすると相手が戸惑う場合があります。
基本的には5,000円〜10,000円の範囲を目安にしましょう。
まとめ:七五三の初穂料の正しい準備で安心して参拝を
ここまで、七五三の初穂料について金額の目安やのし袋の選び方、書き方、渡し方の流れを解説してきました。
大切なのは形式だけではなく、感謝の気持ちを丁寧に表すことです。
ポイントを表に整理すると次のようになります。
| ポイント | 基本ルール |
|---|---|
| 金額 | 一人あたり5,000円〜10,000円。兄弟姉妹は人数分。 |
| のし袋 | 赤白蝶結び。表書きは「初穂料」または「御初穂料」。 |
| 名前 | 子どものフルネームを書く。兄弟は連名でも可。 |
| 中袋 | 表に金額(壱萬円など)、裏に住所と名前。 |
| 封入 | 新札を肖像が上になるように入れる。 |
| 渡し方 | 袱紗から出して「よろしくお願いします」と一言添える。 |
【まとめの例文】
「本日はよろしくお願いいたします。初穂料をお納めいたします。」
「七五三のご祈祷をお願いします。こちらが初穂料です。」
このような一言を添えて渡せば十分に丁寧です。
最後にもう一度確認しておきましょう。
① 金額は一人5,000円〜10,000円
② のし袋は赤白蝶結び、「初穂料」と記す
③ 名前は子どものフルネームを記入
④ 新札を正しい向きで入れる
⑤ 袱紗に包み、受付で一言添えて渡す
これらを守れば、初穂料の準備は完璧です。
きちんとした心構えで臨めば、七五三の参拝を安心して迎えられるでしょう。

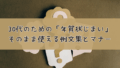
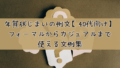
コメント